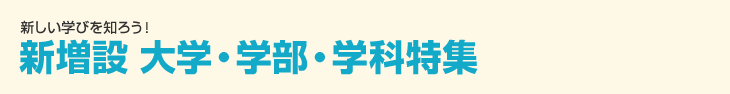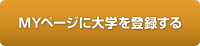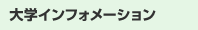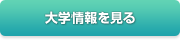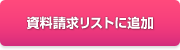跡見学園女子大学

新設学部・学科レポート

実践的なカリキュラムで学生をサポート。女性の視点で「観光」「コミュニティ」をデザインできる人材の育成をめざす
新設予定学部・学科
- ●観光コミュニティ学部/観光デザイン学科、コミュニティデザイン学科
日本の伝統を大切にし、豊かな教養と高い人格を兼ね備えた女性を育ててきた跡見学園女子大学。学園創立140年の転機にあたり、新学部「観光コミュニティ学部」を設置し、社会人として観光立国・日本を担える人材、地域の活性化を支える人材の育成をめざします。
新設の背景
豊かな教養と自由な精神をもつ自立した人材を世の中に輩出してきた女子大学

跡見学園女子大学は1875年(明治8年)、東京・神田に開校した跡見学校をルーツにもつ4年制大学です。学祖・跡見花蹊(あとみ・かけい)が掲げた「日本の誇る伝統文化を踏まえ、豊かな教養と高い人格を持ち、自律し自立した女性を育てる」という建学の精神を受け継ぎ、世の中で必要とされる優秀な人材を多数輩出してきました。時代の新しい要請に応えるため、2002年(平成14年)には、他の大学に先駆けて「マネジメント学部」を設置。社会においてリーダーシップを発揮する女性の育成にも努めています。
学園創立140年・女子大学創立50年を迎える2015年(平成27年)には、新たに「観光コミュニティ学部」の開設を予定しています。観光立国日本を支える人材を育成する「観光デザイン学科」、地域コミュニティの活性化に貢献する人材を育成する「コミュニティデザイン学科」の2つの学科を設置して、教育体制のさらなる充実を図ります。
グローバル化する社会のニーズに応え「観光」「コミュニティ」を学べる新学部を創設
21世紀を迎えた今、日本では「観光」のもつ重要な役割が見直されています。たとえば地元の伝統を生かした新しいイベントやご当地グルメなど、地元の特色を全国にアピールできる観光業により、地域の産業や社会を活性化する動きが各地に広がっています。
一方、グローバル化や少子高齢化など社会の大きな転換期を迎え、私たちの生活の基盤となる「コミュニティ」の大切さが改めてクローズアップされています。自分たちの手で暮らしやすい町を形作り、地域の協力体制や人と人とのつながりを深めることは、将来の日本社会にとって大きな課題といえます。
新学部では、こうした日本の未来を拓く新しい事業の創造を「デザイン」と考え、「観光」「コミュニティ」の側面から地域を活性化させることができる「デザイン能力」を備えた女性を育成。跡見学園の伝統である教養を重んじた教育を基盤としながら、社会に貢献できる実務能力を養う「教養実践」の教育を行います。
学びの内容と特色
観光をテーマに、日本を元気にするための実践的な能力を養成する「観光デザイン学科」

観光デザイン学科では、地域経済の振興と社会の活性化を促すため、地元の人々と協力して観光業を担っていくための専門能力を養うことを目的としています。入学後には、まず観光に関する理論と知識の基礎を学びます。2年次には、全員が観光関連の企業・団体・自治体などでのインターンシップで実務を経験。知識と実践の両面から観光を体験的に学びます。3・4年次には、グローバルツーリズム、観光マネジメント、観光コンテンツの観点から理論と知識を深めます。また、「観光デザイナー特殊演習」などの授業で、具体的な観光課題の解決に挑戦し、観光デザイン能力を高めます。
本学科では、グローバルな視野と国際感覚、高度なホスピタリティ能力を身につけ、旅行・航空業などをめざす「グローバル分野」、観光事業を発展させるマネジメントを学び、宿泊やリゾート、テーマパーク、ブライダル産業などをめざす「マネジメント分野」、名所・名物を発掘して世界に発信する方法を学び、地域振興に取り組む行政や地域産業などでの活躍をめざす「観光振興分野」と、将来の希望に合わせた3つの履修モデルを用意しています。
このほかに、観光業を発展させるために必要な経営やマーケティングに関する知識や、地元の歴史や美しい風景、おいしい食べ物など、これまで気づかれなかった魅力的なヒト、コト、モノを発掘して観光コンテンツとしてブランド化する方法など、様々な分野の学びを用意しています。
新しい地域コミュニティを構築する能力を養う「コミュニティデザイン学科」
コミュニティデザイン学科では、地域住民とともに地域コミュニティの課題を解決するために、必要な専門知識と実践能力を養うことをめざしています。そのため、実際に地域でのフィールドワークを行い、現地・現場の視点から実地で学べる体験実習を必修科目としています。地域に根ざした実践的な学びを通じて、地域のコミュニティが抱える課題を見つけ出す能力、その解決するためのアイデアを生み出す能力、さらに人と人とのつながりを作り出す能力を身につけます。
女性の視点を重視していることも大きな特徴です。地域コミュニティの中で、結婚、出産、子育て、介護といった女性のライフサイクルに関する課題を、女性一人ひとりが自ら主体的に問い直せるよう、教育システムを構築しています。
コミュニティを活性化するさまざまな事業を行政の視点で学ぶ「コミュニティ分野」、地域金融、財政、産業について学び、地域活性化をビジネスの視点で研究する「ビジネス分野」、子育て環境や町づくりなどを学び、地域に根ざした社会貢献に取り組む「社会貢献分野」と、将来の希望進路に応じた3つの履修モデルを用意しています。
大学からのメッセージ
基礎から実践まで体験型の演習・実習科目を充実させた独自のカリキュラムを導入
新学部のカリキュラムは、1・2年次の前期課程と、3・4年次の後期課程で構成されます。前期課程では、観光とコミュニティをめぐる基礎的な知識を修得。観光デザイン学科では観光学、観光デザイン、経営学、また、コミュニティデザイン学科では社会学、コミュニティデザイン、フィールドスタディといった、それぞれの学びの入門科目を履修して基礎力を身につけます。2年次には、学外での実習を含んだ基礎ゼミナール(演習)を配置。体験型の授業により実践力の基盤を築きます。
後期課程では知識の専門性を高め、さらに実践的な訓練を経て、社会で生かせるデザイン能力を育成します。中でも観光デザイン学科における、観光デザイナー特殊演習、キャビンアテンダント(CA実習)、ホテルマネージャー・女将実習、コミュニティデザイン学科における、コミュニケーション、編集・制作、プレゼンテーションなどの各特殊演習など、将来の進路に関連した特殊演習・実習科目が充実しているのが特徴です。
TOPICS
キャンパス近隣の環境から学べるユニークな学部共通科目を配置

観光コミュニティ学部の学生は、1・2年次を自然豊かな新座キャンパス(埼玉県)で、3・4年次を都心にありながら落ち着いた環境の文京キャンパス(東京都)で過ごします。そこで学部共通の専門科目として、1・2年次には、古くは「武蔵野」と呼ばれた新座キャンパスの地域性を生かした「むさしの学」、3・4年次には、我が国有数の教育・研究部門の集積地でもある文京地域について学ぶ「ぶんきょう学」の開講を予定しています。
たとえば「むさしの学」では、小説や映画などで古くから親しまれてきた武蔵野の雑木林に代表される自然景観、歴史、文化など、地域の特性や豊富な文化資源について学習します。「ぶんきょう学」では折に触れて現地調査も予定しており、東京の魅力を学習し、大都市ならではのコミュニティの実態について学習します。いずれもキャンパス周辺にある身近な実例を通じて、観光や地域コミュニティのあり方を理解することができるユニークな科目といえます。