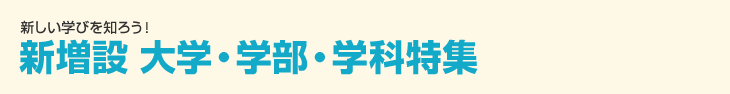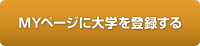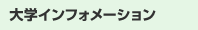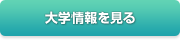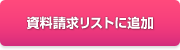工学院大学

新設学部・学科レポート

未来社会を見据えた「先進工学部」を2015年に新設。2016年には「情報学部」が2学科を加えて進化
新設予定学部・学科
- ● 先進工学部/生命化学科・応用化学科・環境化学科・応用物理学科・機械理工学科 ※2015年4月新設
- ● 情報学部/システム数理学科・情報通信工学科 ※2016年4月設置構想中
日本の工学教育をリードしてきた工学院大学では、2015年4月に「先進工学部(生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科、機械理工学科)」を新設。2016年4月には情報学部に「システム数理学科」「情報通信工学科」を設置し、社会のさらなる発展を支える人材を育成します。
新設の背景
工学技術の分野におけるきめ細かな少人数教育により、日本産業界を支えてきた伝統校

工学院大学は、1887年(明治20年)に創設された「工手学校」をルーツにもち、日本産業界を支える工学技術者の人材を多数輩出してきた伝統ある大学です。現在、教育研究の基本的な拠点である研究室の数は合計156にのぼり、1研究室あたり平均9人という少人数制により、きめ細かな教育体制を築いています。
人類社会が抱える重要な課題を解決するためには、科学技術の力で社会を進化させることが必要になっています。そこで、工学院大学では2015年4月に新しく「先進工学部」を設置。「生命化学科」「応用化学科」「環境化学科」「応用物理学科」「機械理工学科」の5学科を配置します。2016年4月には情報学部に新たに「システム数理学科」「情報通信工学科」を設置し、教育研究体制をいっそう充実させます。
従来からのバランスある人格教育を継続して実践するとともに、近未来技術と情報技術を通して、社会のさらなる発展に貢献できる人材を育成することをめざします。
高度な工学知識を、先進的な発想で新規開発につなげる工学技術者を養成する「先進工学部」
現代が抱える地球的問題を解決するには、長期的な取り組みと国境を超えた協力体制が重要です。それには、既成概念にとらわれない先進的な発想力と、その発想を技術に展開して社会に普及させる工学知識が不可欠となります。
そこで先進工学部では、学部の共通カリキュラムとして新しい発想の源である「基本原理」の学びを重視し、低学年で徹底的に身につけます。1年次には数学、物理学、化学など幅広い自然科学の基本を学び、自らの知識を柔軟に融合・応用する力を修得します。2年次以降は各学科の専門科目に軸足を置きつつ、多様な専門分野を横断的に学びます。
また、1年を4期に分ける「クォーター制」を採用。短いサイクルで一人ひとりの学修進度や関心に応じた履修スタイルが選べるうえ、学期制の異なる海外への留学にも柔軟に対応できるメリットがあります。
工学院大学・先進工学部のスペシャルWebサイト(上画像)では、さらに詳しい情報を掲載しています。こちらも参照してください(http://www.kogakuin.ac.jp/ae/)。
情報技術を活用し、社会に新たな価値を生み出せる工学技術者を養成する「情報学部」
情報学部では、これまで「コンピュータ科学科」「情報デザイン学科」の2学科で、豊かな情報社会の実現に向けて中核となる人材を育成してきました。
日常的にたくさんの情報が流れる日本社会では、政治、経済、文化、国際など、あらゆる側面で情報の活用が進み、情報関連の学問がますます重要になっています。そこで新たに「システム数理学科」「情報通信工学科」を開設。4学科で情報学の幅広い領域を網羅する新体制を整えます。
生まれ変わる情報学部では、まず学部共通のプログラムで情報学のベースとなる「数学」と「プログラミング」を重点的に学び、そのうえで各学科の専門科目を中心に多様な分野を深く研究します。めざしているのは「高度情報社会において、情報を軸に社会システムを企画・構築・運用し、豊かな社会をデザインしていくリーダーとなれる技術者」の育成。卒業後は、情報関連をはじめとする産業界で、情報を有益に活用して新たな価値を創造できる人材としての活躍が期待されます。
学びの内容と特色
■先進工学部
化学者として、生命を学び、生命に学ぶ「生命化学科」

生命化学科では、生命の営みを学ぶ「生命科学」と有機化合物の合成を学ぶ「有機化学」の両方を修得し、さらに双方の考え方を「ケミカルバイオロジー」のキーワードでつなぎます。講義や実験・実習を通じて複雑な生命現象を化学というシンプルな言語で理解し、表現する力を養います。さらに有用な化学物質を創出し、医薬品や医療技術の開発、生物資源の有効利用に応用することで、社会に貢献できる研究者・技術者を育成します。
「くらし」を支え「みらい」を拓く「応用化学科」
応用化学科では、化学の基礎となる5科目(無機化学、有機化学、生物化学、物理化学、分析化学)を土台にして専門性を磨くとともに、ものづくりの素養も修得します。3年次から、高分子やナノテクノロジーなど最先端分野の技術開発に取り組む「応用化学コース」と、食品品質管理や環境浄化など、暮らしに密着した分野の研究に進む「生活・食品化学コース」の2つにコースに分れます。1コースに軸足を置きつつ連携する分野を複合的に学べます。
豊かな自然と快適な生活を化学で実現する「環境化学科」
環境化学科では、大気・水・土壌の分析と保全を行う「環境システム工学」、新エネルギーや新素材を開発する「環境材料化学」、環境への影響を評価する技術を学ぶ「環境評価・設計」という3つの領域を横断的に学ぶことで、環境を保全する技術や環境負荷を低減する技術を開発し、持続可能な社会に貢献できる技術者・研究者を育成します。
物理の発想で工学の新たな可能性を拓く「応用物理学科」
応用物理学科では、基礎として物理を学び、数学を道具として使用し、ものづくりに応用する工学のセンスを身につけます。物理学と工学にまたがる4領域(物性・材料、物理情報計測、エレクトロニクス、物理・応物一般)を幅広く学び、物理学と工学を融合した研究環境を通して、専門領域を超える柔軟な発想力と実践的な研究開発能力を持ったエンジニアを育成します。
社会が抱える課題をグローバルな視点で捉え解決する「機械理工学科」
機械理工学科では、数学や物理などの基礎力と工学の基礎知識を応用して、グローバルな規模で社会的、工学的課題を解決する能力を養います。機械系の専門科目に加え、専門分野について英語でコミュニケーションできる能力を「技術英語」で、企業との共同研究で課題解決力を「産学連携プログラム」で身につけます。
■情報学部
社会システムを企画・構築できる人材を育てる「システム数理学科」

システム数理学科は、情報分析から経営戦略立案まで、企業での情報の扱い方をトータルに学べるのが特徴です。企業に集まる情報を分析し、得られた成果をもとにしてシステムを構築できる能力を身につけます。さらに大量のデータを処理・分析する際に有効な「ビッグデータ」を扱うための実践的なデータ科学を修得することで、経営戦略、マーケティング、企業情報戦略などの分野で、組織をリードできる技術者を養成します。
情報と通信とデバイスを総合して、多様なIT技術者を育てる「情報通信学科」
情報通信工学科は、情報と通信とデバイスの分野を総合的に学べるのが特徴です。情報社会の基盤であるネットワークや通信技術、デバイスについて、その操作原理から応用システムまでを理解することをめざします。最新の技術動向を反映した授業を豊富に用意。「無線従事者」「電気通信主任技術者」など、企業からの需要の多い資格取得につながる教育内容により、即戦力として社会で役立つ実践力が養われます。
大学からのメッセージ
幅広い産業分野へ、質の高い就職支援実績を支える「的確かつきめ細かな」支援
工学院大学では、学部系列ごとに築いたきめ細かな就職支援体制、そして就職支援センターの職員による社会のニーズを踏まえたサポートによって、95.1%(2013年度)という就職内定率をあげています。たとえば、インターンシップや留学先における各業界での就業体験、学内で実施している合同説明会など、さまざまなキャリア支援を通して学生の視野を広げ、学生1人ひとりの適性や目標に合った就職をサポートしています。さらに、各種対策講座や独自セミナーの開催、第一線でキャリアを積んだ社会経験の豊富なアドバイザーの常駐など、万全の体制を敷いています。
学生1人あたりの求人件数を示す有効求人倍率は5倍を超え、他大学と比較しても工学院大学生に対する企業採用ニーズは非常に高いといえます。120年を超える歴史の中で累計10万人を数える卒業生は、工学分野の隅々までに広がっており、先輩たちの活躍のおかげで業界からの厚い信頼を獲得しています。
TOPICS
日本初!日本語で学び、英語で生活するハイブリッド留学プログラム

工学院大学では、急速にグローバル化する社会で生き抜いていく人材を育成するため、「ハイブリッド留学プログラム」を展開しています。
この留学制度では、従来の参加条件を緩和して「英語力は不問」とし、留学への高いハードルをなくしました。現地では、専門科目は渡航した担当教員が日本語で実施します。英語の授業は提携校のネイティブの教員が担当。滞在中の日常生活はホームステイで英語力を磨く“ハイブリッドな環境”を実現しています。現地での授業料は不要で、工学院大学の学費のみで受講でき、しかも帰国後には正規の単位として認められる画期的なプログラムです。
先進工学部、工学部、情報学部はアメリカ・シアトル、建築学部はイギリス・カンタベリーでのプログラムが用意されています。