インターンシップとは?大学生が参加できるインターンシップの種類や目的、参加方法を解説
2025.07.25

「大学生はいつからインターンシップに参加できる?」
「大学生がインターンシップで何をするのか知りたい!」
高校生の皆さんの中には、インターンシップと聞いてこのように考えている人もいるでしょう。
インターンシップは、学生のうちから興味のある企業で仕事を体験できる「就業体験」です。インターンシップへの参加は就職活動に必須ではありませんが、就活に有利に働く可能性があるともいわれています。
この記事では、インターンシップの種類や目的、インターンシップのために大学生のうちからできることについて解説しています。大学1年生・2年生のうちからすべきことについても触れているので、参考にしてみてください。
目次
- 1 インターンシップとは
- 2 インターンシップの目的
- 3 インターンシップの内容
- 4 インターンシップとアルバイトの違い
- 5 インターンシップのメリット
- 6 インターンシップの実態調査
- 7 インターンシップの定義
- 8 【大学1年生・2年生】タイプ1:オープン・カンパニー
- 9 【学士・修士・博士課程】タイプ2:キャリア教育
- 10 【大学3年生・4年生・修士1年・2年】タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
- 11 【大学院生】タイプ4:高度専門型インターンシップ
- 12 インターンシップの流れ
- 13 インターンシップを探す
- 14 インターンシップが実施されるのは長期休暇
- 15 インターンシップのために大学1年生・2年生のうちからできること
- 16 自己分析をする
- 17 業界研究をする
- 18 オープン・カンパニーに参加する
- 19 求人サイトに登録する
- 20 大学生からインターンシップに参加して理想の企業に就職しよう
インターンシップとは

インターンシップの目的や内容など、インターンシップの基本的な概要について解説します。
インターンシップの目的
インターンシップは企業が実施する職業体験プログラムで、学生が企業や職務への理解を深めることが目的です。インターンシップで実際の仕事を経験することで、学生は仕事への理解を深め、自分に合った職業を選びやすくなるでしょう。
企業側としても、学生の価値観やポテンシャルを知りたい、就職後のミスマッチを防ぎたい、といった目的があります。
インターンシップの内容
インターンシップの内容は業界や企業によっても異なりますが、学生が企業の理解を深めるため、主に下記のような内容が行われることが多いようです。
● グループワーク
● 若手社員との交流会
● 社員による講義・レクチャー
● ロールプレイング形式の仕事体験
● 工場・職場見学
● 実際の現場での仕事体験
また、近年では対面に限らず、オンラインでインターンシップを開催する企業も増えてきています。
インターンシップとアルバイトの違い
実際に社会人経験を積めるという点ではインターンシップとアルバイトは似ていますが、目的が異なります。
アルバイトの場合、企業は労働力の確保を目的に人を募集します。募集対象も高校生以上と幅広く、応募する側も給料を得ることを目的としています。
一方インターンシップの場合、企業は学生に仕事を体験してもらうことを目的に募集します。募集対象は大学生以上に限られ、応募する側も給料を得ることより仕事を体験すること、企業を知ることを目的としているのがほとんどです。
インターンシップのメリット
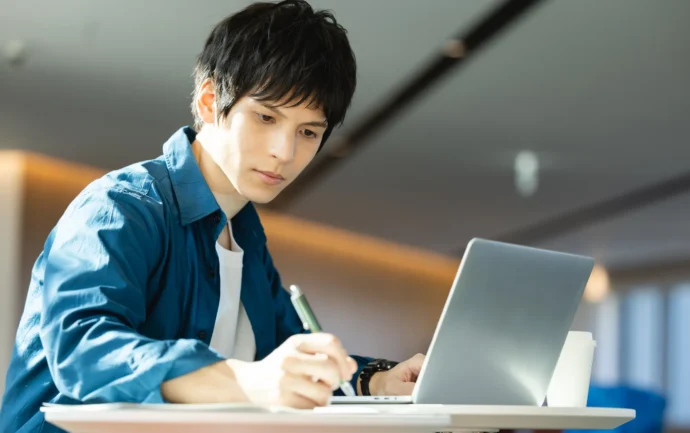
インターンシップに参加すると、インターンシップを通じて企業・業界研究を進めることができます。事前に職場の雰囲気や仕事の実態を知ることで、就職してから想像と違った、というようなミスマッチも防ぐことができるでしょう。
また就活において、面接時に聞かれるガクチカやエントリーシートに自身の経験として盛り込むことができ、就活を有利に進めることもできます。
ガクチカやエントリーシートについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も読んでみてください。
インターンシップの実態調査
実際にインターンシップに参加した大学生の体験談や、どれくらいの大学生がインターンシップを経験しているのか、などのデータを簡単にまとめました。
インターンシップに参加している大学生は約90%
調査によると25年卒の大学生のうち、約90%がインターンシップに参加していました。その中でも5日以上の長期インターンシップに参加した大学生は20%程度です。
インターンシップの平均応募社数は約12社
インターンシップは複数応募することができますが、応募した会社の数は平均で約12社という結果になりました。インターンシップへの参加でも選考が行われるため、実際に参加した会社は平均9社という結果になっています。
1日のみの短期インターンや、日数のかからないオンラインインターンであれば、複数のインターンシップに参加することができます。希望の企業や業界が定まらない大学生の多くは、企業や業界を知るために複数のインターンシップに参加するようです。
実際に複数のインターンに参加した大学生からは、「様々な業界を見たことで新しい事柄に興味を持ちやすくなり、より意欲的に勉学に取り組めた」「自分の専門分野がどのように社会に貢献しているかを学べ、学業のモチベーションになった」といった声も上がっています。
インターンシップに参加した大学生の約80%が同じ会社に就職している
就職希望企業のインターンシップに参加した大学生のうち、約80%が同じ企業に就職していることがわかりました。インターンシップを通じて実際の仕事のことや現場の雰囲気を知ることで、入社の決め手となった大学生は多いようです。
<参考>
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/202503_internship_chosa.pdf
https://shushokumirai.recruit.co.jp/research_article_topics/20241129001/
https://www.y-aoyama.jp/unicari/internship/1608/
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20231027_63679/
インターンシップの定義

インターンシップは国によって定義されており、令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変更されています。
文部科学省・厚生労働省・経済産業省の3省合意によって、「インターンシップの推薦に当たっての基本的考え方」が改正されました。これまではインターンシップと総括して呼んでいた取り組みを4つに分類しなおし、学業に影響が出ないように配慮しつつ学生のキャリア形成をサポートすることになったのです。
タイプによって、対象年次も定義されています。対象ごとにひとつずつ簡単に解説します。
【大学1年生・2年生】タイプ1:オープン・カンパニー
オープン・カンパニーは、企業や業界についての理解を深めるための情報提供が主な目的です。具体的には、就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベント・説明会などがオープン・カンパニーに該当します。
基本的に一日程度で終了することが多く、定義によってインターンシップとは呼ばれないものの、短期インターンに分類されます。
【学士・修士・博士課程】タイプ2:キャリア教育
キャリア教育は、就業体験を必須とせず職業についての基礎知識やスキルを学ぶことが目的です。タイプ1と同様にインターンシップという呼称は使いませんが、短期インターンに分類されます。
キャリア教育には企業主催のプログラムと大学主催のプログラムがあり、企業主催の場合は学士・修士課程のみを対象、大学主催の場合は学士・修士・博士課程を対象とする違いがあります。
【大学3年生・4年生・修士1年・2年】タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
汎用的能力・専門活用型インターンシップは、学生が実際の業務を通じて汎用的なスキルや専門的なスキルを磨くことを目的としています。
一般的にイメージされるインターンシップが該当し、「汎用的能力活用型」は5日間以上、「専門活用型」は2週間以上の参加が必要とされるため、長期インターンに分類されます。
タイプ1との大きな違いは、就業体験を必須とする点です。また、大学の場合は3年生・4年生が参加対象です。
【大学院生】タイプ4:高度専門型インターンシップ
高度専門型インターンシップは、学生が特定の分野における実務経験を通じて自身の専門性を高めることを目的としています。参加対象は大学院生です。
タイプ3と同様に長期インターンに分類されますが、インターンシップの期間は半年から1年ほど、長くて2~3年にわたるケースもあります。
インターンシップの流れ

インターンシップの基本的な流れについて説明します。インターンシップはタイミングを逃すと参加や申し込みができなくなってしまうため、大まかな流れを把握しておきましょう。
インターンシップを探す
インターンシップに参加・申し込みするためには、インターンシップを探す必要があります。タイプ3やタイプ4の長期インターンシップに参加申し込みするには、インターンシップを紹介しているサイトや派遣会社で探すと良いでしょう。
インターンシップの参加にも選考があり、応募したインターンに必ず参加できるとは限りません。そのため、優先順位を決めて複数のインターンシップにエントリーしておきましょう。
タイプ1やタイプ2の場合は、各種就職サイトや求人検索エンジンで探すことができます。既に気になる企業がある場合は、企業の採用ページでも確認できるので、早めに情報を集めるようにしましょう。
インターンシップが実施されるのは長期休暇
長期のインターンシップは5日以上の就業体験を必要とするため、学業の妨げにならないよう長期休暇に実施されることが多いです。
募集は一般的に実施時期の2~3ヵ月前に行われるため、夏休み・冬休みの前にはこまめに情報をチェックしておきましょう。
インターンシップのために大学1年生・2年生のうちからできること
インターンシップに参加できるのは大学3年生からですが、大学1年生・2年生のうちから準備できることはあります。具体的にできることを紹介しましょう。
自己分析をする
インターンシップに参加する前に、充分に自己分析をしておきましょう。
これまでの経験や行動を思い返し、そのような選択をした理由、何を学んだかを把握することで、自己分析を進められます。自己分析によって自分の強みを明確にしておくと、インターンシップに応募する企業を探すときの指標になります。また早いうちに強みや弱みを理解しておけば、学生時代の中で改善することもできるでしょう。
業界研究をする
業界研究とは、各業界の特徴や規模・動向・仕事内容などを調べることです。
業界や企業のことを知らなければ、応募するインターンシップを選ぶこともできません。大学1年生・2年生のうちから業界研究を進めておくことで、幅広い業界の中から自分の希望する業界を選ぶことができ、興味のある企業を見つけることもできるでしょう。
オープン・カンパニーに参加する
前述した定義によるタイプ1に該当する、オープン・カンパニーに参加してみましょう。オープン・カンパニーは全学年を対象とし、短期間で実施されるプログラムであるため、気軽に参加しやすいです。
興味がある業界のプログラムに参加しておくと、業界の雰囲気や仕事内容を知ったうえでインターンシップに参加できるでしょう。
求人サイトに登録する
求人サイトに登録して、情報を集めておくのも良いでしょう。
求人サイトではどのような求人があるのか、企業がいつ頃インターンシップを募集しているのかを知ることができます。早いうちから情報を集めておくと、インターンシップに申し込むタイミングを逃さずに済むでしょう。
こちらの記事では、就活のより細かいスケジュールについて解説しています。自己分析や業界研究を始める時期や、企業や業界によって異なるインターンシップのスケジュールについても触れているので、読んでみてください。
大学生からインターンシップに参加して理想の企業に就職しよう

大学生のインターンシップについてまとめました。
インターンシップは学生が就業前に職業体験をするためにおこなわれ、参加すると企業をよく知ることができ、就職後のミスマッチを防ぐことができます。
自己分析をしたり、オープン・カンパニーなどのプログラムに参加したり、大学1年生・2年生のうちからできることもあります。充分に準備をしてインターンシップに参加すれば、理想の企業に就職できる確率は高まるでしょう。
「biki-note」では業界や職種を紹介する記事を掲載しています。インターンシップに応募する企業や業界を選ぶときや、業界研究に役立ててみてくださいね。

