ケースワーカーとは?仕事内容や必要な資格、主な職場、年収を解説
2022.10.25
最終更新日: 2025.04.17

「ケースワーカーってどんな仕事なの?」「資格は必要?」といった疑問を持つ人は多くいます。正確な情報を知らずに目指すと、想像と違う仕事だったり、必要な資格が取得できなかったりする場合もあるため、注意が必要です。
この記事では、ケースワーカーの基本的な仕事内容や主な就職先、必要な資格、将来性などについて解説します。ケースワーカーになるための進路も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください! ケースワーカーを目指せる大学・学科を知りたい人は「系統別学問内容リサーチ」で、名前に「福祉」がつく学科を見てみましょう。設置されている大学もあわせて確認できますよ!
目次
ケースワーカーとは?
ケースワーカーとは、何らかの理由により日常生活の困難に直面している人々に対して、相談や援助などの業務を行う職種です。「Case Worker」の頭文字を取って「CW」と表記されることもあります。
ケースワーカーの仕事では、高齢者への福祉施設や介護施設の紹介、生活保護受給者への自立支援など、相談者の状況に応じた福祉サービスを提供していきます。
福祉事務所や児童相談所で働くケースワーカーは地方公務員です。そのため、公務員試験に合格する必要があります。介護施設や病院などでは、民間の職員としてケースワーカー業務に携わることもあります。
福祉事務所などに配属された場合、相談窓口で支援申請を受け付ける面接担当と、定期的な家庭訪問を行い状況を把握する地区担当に分かれて活動するのが一般的です。
1人で数十世帯を受け持つケースが多いので、それぞれの人に合わせて適切な援助をする大変さもあるでしょう。それでも、相談者が不安なく生活できるようになったときに、とても大きなやりがいを感じる仕事といえます!
ケースワーカーとソーシャルワーカーの違い
ケースワーカーと似た職業に「ソーシャルワーカー」があります。両者とも、福祉の現場で困っている人の助けになる点では一緒ですが、必要な資格や勤務先が異なります。
| ケースワーカー | ソーシャルワーカー | |
| 必要な資格 | 社会福祉主事任用資格 児童福祉司任用資格 | 必須の資格はなし |
| 主な就職条件 | 地方公務員試験に合格 | 各施設や機関の採用条件による |
| 主な勤務先 | 福祉事務所や児童相談所などの公的機関 | 高齢者福祉施設や医療機関、福祉サービスを行う民間企業など幅広い |
ケースワーカーの勤務先は、公的機関である福祉事務所や児童相談所などが一般的です。
福祉事務所で働くには、「社会福祉主事任用資格」を取得し、地方公務員試験に合格する必要があります。児童相談所で働く場合は「児童福祉司任用資格」を取得したうえで、地方公務員試験に合格する必要があります。
一方、ソーシャルワーカーを名乗るのに必須の資格はありませんが、応募条件として、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を掲げている施設が多いです。ソーシャルワーカーの勤務先は幅広く、高齢者福祉施設や医療機関、福祉サービスを行う民間企業などがあります。
最近の傾向としては、社会福祉士や精神保健福祉士をはじめとする国家資格を持つ人を、まとめてソーシャルワーカーと呼ぶことが増えているようです。つまり、ソーシャルワーカーは福祉全般の相談員を指す広い概念で、ケースワーカーはそのなかでも主に福祉事務所などの公的機関で働く人を指します。
ケースワーカーの仕事内容

ケースワーカーの仕事内容は、以下のとおりです。
- 面談の実施
- 支援計画の作成
- 支援の実施と手続き
- 家庭訪問の実施
- 支援の評価と調整
まずは、生活に困難を抱える人やその家族との面談を行い、問題の詳細や支援の必要性を把握します。
次に、問題解決に向けて具体的な支援計画をたて各種手続き等を行います。たとえば、生活保護の申請支援や高齢者福祉施設への入居手続きの支援などです。ときには、医療機関や介護施設などと連携を取り、支援者が適切に支援を受けられるよう手配します。その後、定期的に相談者の自宅を訪問し、生活状況や健康状態を確認します。家庭訪問の目的は、相談者の健康状況のチェックや生活保護の不正受給阻止などです。
ケースワーカーの主な職場
ケースワーカーの主な職場は、以下のとおりです。
- 福祉事務所
- 病院
- 児童相談所
- 介護施設
順番に解説します。
福祉事務所
福祉事務所は、法律で定められた援護や育成、更生のサポートを行う行政機関です。都道府県と市への設置が義務づけられており、町村は任意で設置することができます。
市役所の福祉窓口で生活保護を担当している職員は、実は「市役所の人」ではなく「福祉事務所の人」です。福祉事務所は市役所内に設置されていることが多いため混同されがちですが、法律上は別の行政機関として位置づけられています。
ケースワーカーは「児童福祉士」や「老人福祉指導主事」などのさまざまな専門家と連携を取りながら、困っている人々の相談に乗っていきます。
児童相談所
児童相談所では、困っている人との面談や家庭訪問を通じて、子どもたちやその家庭が抱える、さまざまな問題の解決に努めます。相談内容によっては、利用できる公的補助制度を調べるなど、その人の状況に合わせてサポートしていきます!
病院
ケースワーカーが病院で働く場合、医療や介護に関する相談を中心として対応することになります。具体的には、医療保険の利用方法や、介護に関する悩みなど、さまざまな相談が寄せられるそうです! ときには患者さん本人だけでなく、その家族から相談される場合もあります。専門的な内容については、医師やケアマネージャーなどと連携しながら、適切なアドバイスをすることが大切です。
介護施設
介護施設には、デイサービスやショートステイ、特別養護老人ホームなどがあり、そこでケースワーカーとして働く人もいます。
介護施設に勤めるケースワーカーは、生活相談員という役職で呼ばれることもあります。主な仕事内容は、施設を利用する高齢者やその家族からの相談に応じ、新しいサービスを利用するための手続きをサポートすることです。また、ケアマネージャーをはじめとする関係者と連絡を取り、利用者に最適なサービスを提供するための連携を図ります。介護施設でケースワーカーとして働く際には、社会福祉主事任用資格や社会福祉士の資格が求められるケースもあります。
ケースワーカーの1日
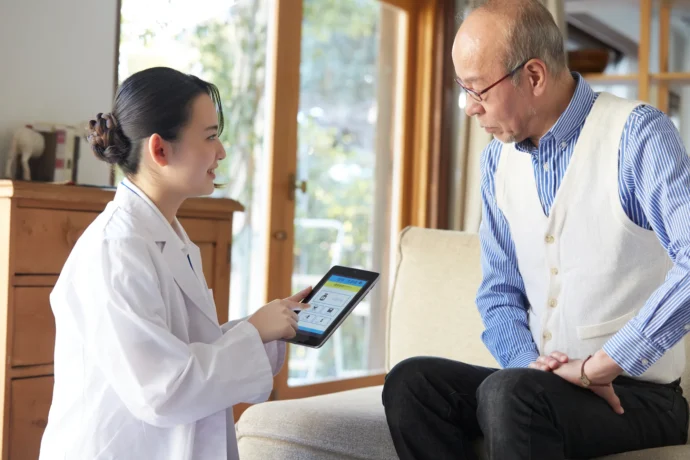
福祉事務所で働く生活保護担当のケースワーカーの1日を紹介します。
| 8:20 | 出勤 |
| 8:30 | 一日のスケジュールの確認 |
| 9:00 | 援助方針や指導内容について検討 |
| 10:00 | 市民や関係機関からの問合せ対応 |
| 12:00 | 昼食休憩 |
| 13:00 | 生活状況を把握するための家庭訪問 |
| 16:00 | 記録の作成、保護費算定のための事務処理 |
| 17:30 | 書類を整理し、翌日の準備をして退庁 |
参照:先輩職員からのメッセージ ~社会福祉~|広島市職員採用情報サイト
生活保護ケースワーカーの主な役割は、経済的に困窮している方々の生活を保障しながら、自立への道筋を支援することです。保護費の計算といった事務処理だけでなく、定期的な家庭訪問を通じて、一人ひとりの生活実態を把握します。そして、それぞれの状況や課題に合わせた適切な支援プランを提案します。 若年層から高齢者まで幅広い年齢層を対象とするため、福祉や医療・就労など多方面の知識が求められるのが特徴です。
ケースワーカーの平均年収
厚生労働省の調査によると、福祉事務所のケースワーカーの年収は425.8万円、月収は22.5万円となっています。金額は就職先によって変わりますが、福祉施設をはじめとした公的機関で働くケースワーカーは公務員であり、社会的な信用度が高いのが魅力です。収入も安定している傾向にあり、勤続年数や新たな資格の取得によってキャリアアップしやすいといえるでしょう。
また、業務内容にもよるものの、自治体や施設によっては特別手当が支給されるケースもあるようです 。
【参照】福祉事務所ケースワーカー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET)) (mhlw.go.jp)
ケースワーカーのやりがいと大変なところ

ケースワーカーの仕事には、以下のようなやりがいと大変さがあるようです。
【ケースワーカーのやりがい】
- 困難な状況にある人々の力になれること
- 支援を通じて、相談者の人生が好転するのを見られること
- 社会の役に立っているという実感が得られること
【ケースワーカーの大変なところ】
- 相談者の抱える問題が複雑で、解決が難しいことがあること
- 行政との調整や書類作成など、事務作業が多いこと
- メンタル面でのストレスがたまりやすいこと
ケースワーカーは、人のために尽くせるやりがいのある仕事である一方、重圧とストレスを感じることもあります。たとえば、認知症や障害を持つ人の苦しみに寄り添う場面や、育児放棄やDVの実態を目の当たりにすることもあるでしょう。
相談者の人生に関わる重要な役割を担っているからこそ、精神的なプレッシャーを抱えやすいのです。そのぶん、利用者の人生をより良い方向へ導けたときは、大きなやりがいを感じられるでしょう。
参考:先輩職員からのメッセージ ~社会福祉~ – 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)
社会福祉士の大変さや苦労|日本福祉教育専門学校 (nippku.ac.jp)
ケースワーカーの将来性
日本では生活保護を受けている世帯が増え、少子高齢化が進んでいることを考慮すると、今後ケースワーカーの必要性がさらに増していくことが予想されます。
日本における生活保護の割合は、年々増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると令和6年度の被保護実人員は約201万人、生活保護受給世帯は約165万世帯です。そのうち高齢者世帯が約90万世帯以上を占めており、高齢化社会が進み続けることよりケースワーカーの需要は高まるといえるでしょう。
また、社会では生活保護の不正受給が大きな問題となっています。大切な生活保護の制度を守り、必要な人たちに支援を届けるには、不正を防ぐ仕組みも欠かせません。こうした不正に対して厳しく目を光らせる役割も、ケースワーカーに求められています。
さらに、高齢者が多い地域では、介護や福祉に関する相談も多くなります。さまざまな観点から解決の糸口を見つけて、必要な施設や専門家への橋渡し役となるケースワーカーは、とても大切な存在なのです!
参照:生活保護の被保護者調査(令和6年7月分概数)の結果を公表します |厚生労働省
ケースワーカーに向いているのはどのような人?

ケースワーカーの仕事に適性がある人の特徴は、以下のとおりです。
- コミュニケーションが得意な人
- 人の役に立つ仕事に就きたい人
- 客観的な立場から対応できる人
- 地道な努力を継続できる人
- 事務作業を着実にこなせる人
コミュニケーションが得意な人
ケースワーカーの業務は、相談者と向き合いながら問題を解決することが中心です。そのため、ケースワーカーとして活躍するには、傾聴力やコミュニケーション能力が必要不可欠!
相談者のなかには、自分の気持ちを表現するのが苦手な人もいるでしょう。そのような場合、ケースワーカーが相手の気持ちを汲み取り、何を求めているのか理解する必要があります。また、相談をもとに提案や助言を行う際は、相手を嫌な気持ちにさせないよう注意しなければなりません。このように、ケースワーカーには高いコミュニケーション能力が要求されます。
人の役に立つ仕事に就きたい人
ケースワーカーとして働くには、相談者からの信頼を獲得する必要があります。そのためには「人の役に立ちたい」という強い意志も欠かせません。奉仕の精神を持って病気や貧困などで苦しんでいる人々に寄り添い、適切な援助方針を策定することが求められます。
特にケースワーカーとして働き始めたばかりの頃は、先輩職員と比べて知識や対応力の面でも劣る可能性があります。そのような場合でも、困っている人を助けるという情熱だけは忘れずに相談者と向き合うことが大切なのです。
客観的な立場から対応できる人
ケースワーカーは、あくまで相談者のアドバイザーという立場を崩してはいけません。相談者へ感情移入するあまり適切な距離感を見失ってしまうと、必要なアドバイスができなくなり、信頼関係が失われる可能性があります。相手を助けるという情熱は持ったまま、一歩引いた視点で冷静に物事を判断し、臨機応変に対応できる人がケースワーカーに向いているかも?
地道な努力を継続できる人
相談窓口に訪れる人のなかには、簡単に解決できない悩みを抱える人も多くいます。ケースワーカーだけでは対処が難しい場合は、専門家や地方公共団体などと協力しながら対応するケースもあります。そのため、ケースワーカーには難題に直面した場合でも粘り強く解決策を模索し、必要な努力を積み重ねられる人でないと厳しいかもしれません。
事務作業を着実にこなせる人
ケースワーカーは、各種申請に必要な書類の作成や相談内容に関する記録などの事務作業も行います。相談者の悩みを解決するために、地味な事務作業を投げ出さずにコツコツとこなせる人ほどケースワーカーに向いていると言えるでしょう!
ケースワーカーになるために必要な資格

ケースワーカーとして民間の施設で働く場合は、特に資格は必要ありません。ただし、公務員として働く場合は、以下の資格が求められます。
- 社会福祉主事任用資格
- 児童福祉司任用資格
- 社会福祉士・精神保健福祉士
どのような職場でどの資格が必要なのか解説します。
社会福祉主事任用資格
ケースワーカーとして福祉事務所で働くためには、社会福祉主事任用資格を取得することになります。具体的には、資格を取得したうえで地方公務員試験に合格し、社会福祉主事として福祉事務所に配属される流れです。
任用資格とは、公務員が特定の業務を行う際に必要となる資格です。社会福祉主事任用資格は、そのうち公務員が公的機関で福祉職に従事するために必要な資格を指します。ただし、資格を取得したケースでも、福祉事務所に配属にならない場合は社会福祉主事を名乗ることはできません。
社会福祉主事任用資格は、取得のハードルが比較的低いのが特徴です。資格試験を受験する必要はなく、大学や短大、養成機関(専門学校や通信課程)で指定科目を履修して卒業するだけで取得できます。そのほかには、都道府県が開催している講習会で指定科目を修了することでも取得が可能です。
社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格を持っている人は、社会福祉主事任用資格の取得は免除されます。
児童福祉司任用資格
児童相談所で働くケースワーカーは「児童福祉司任用資格」が必要となります。児童福祉司任用資格は、福祉系の大学や短大に進学し、必要な科目を履修するか、社会福祉主事として児童福祉事業に2年以上従事することで取得可能です。
資格取得後は、公務員試験に合格する必要があります。なお、医師免許、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を持っている場合は、取得が免除されます。
社会福祉士・精神保健福祉士
社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている場合は、自動的に社会福祉主事任用資格、児童福祉司任用資格の保有者とみなされ、ケースワーカーとして働くことができます。
どちらも福祉分野の専門家であることを証明する国家資格で、社会福祉主事任用資格や児童福祉司信用資格と比べると取得は難しいですが、資格を持っていればきっと現場で頼られる活躍ができるはず!
社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っていれば、就職先の幅が広がるため、進路に悩んでいる場合はこれらの資格を目指せる大学などを探すのもおすすめです。社会福祉学科(専攻)や精神保健福祉学科(専攻)を視野に入れてみては?
ケースワーカーを目指せる大学・学部
ケースワーカーに必要な社会福祉主事任用資格や児童福祉司任用資格は、福祉系の学部で取得できます。福祉系の学部を設置している大学の一例は、以下のとおりです。
【国公立】
- 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 (神奈川県)
- 岡山県立大学 保健福祉学部 現代福祉学科(岡山県)
- 山口県立大学 社会福祉学部 社会福祉学科(山口県)
【私立】
- 立正大学 社会福祉学部 社会福祉学科(埼玉県)
- 城西国際大学 福祉総合学部 福祉総合学科(千葉県)
- 佛教大学 社会福祉学部 社会福祉学科(京都府)
- 日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科(愛知県)
- 九州医療科学大学 社会福祉学部 スポーツ健康福祉学科(宮崎県)
【通信】
- 日本医療大学 総合福祉学部 ソーシャルワーク学科(北海道)
- 東京福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科(東京都)
- 早稲田大学 人間科学部 健康福祉科学科(埼玉県)
ほかにも、ケースワーカーを目指せる大学を知りたい人は、「系統別学問内容リサーチ」で、名前に「福祉」がつく学科を見てみましょう。設置されている大学もあわせて確認できますよ!
ケースワーカーになったあとのキャリアパス

ケースワーカーになった後のキャリアプランには、以下があります。
- 査察指導員(スーパーバイザー)
- 社会福祉士や精神保健福祉士
査察指導員(スーパーバイザー)
ケースワーカーとして実務経験を経たあと、査察指導員(スーパーバイザー)へとキャリアアップする道があります。査察指導員(スーパーバイザー)は、ケースワーカーチームを統括し、支援の質を高める役割を担います。
ケースワーカーへの定期的な指導・助言、複雑なケースへの介入支援、支援計画の評価・承認などが主な仕事です。また、組織と現場の橋渡し役となり、現場の課題を管理職に伝えるのも重要な役割です。
社会福祉事業法に基づき、ケースワーカー7名に対してスーパーバイザーを1名以上配置することが義務化されています。
社会福祉士や精神保健福祉士
ケースワーカーとして実務経験を積んだあと、社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を取得してキャリアアップする道があります。これらの資格を持つと、より専門的な相談支援や福祉サービスのコーディネート業務に携わることが可能です。
社会福祉士になるには複数のルートがあります。社会福祉主事として実務経験を積んだ場合、一般大学卒業者よりも短い期間で受験資格を得られます。すでに指定科目を履修していれば最短2年、実務経験が4年以上あれば養成施設への通学が必要です。
学歴や経験によって必要な通学期間は異なりますが、いずれの場合も所定のカリキュラムを修了し、国家試験に合格する必要があります。
ケースワーカーへの道を「JOB-BIKI」で確認しよう!
今回は、ケースワーカーの仕事内容や就職先、必要な資格、将来性についてお伝えしました。ケースワーカーは、さまざまな理由により生活上の困難に直面した人々に、手を差し伸べられるやりがいのある仕事です。「人の役に立つ仕事がしたい」と思っている人にとっては天職といえるかもしれません。
ただし、ケースワーカーとして就職する場合、施設によっては一定の資格が必要になるケースがあります。資格の取得に必要な授業を受けられる大学を探している場合は 「JOB-BIKI(ジョブビキ)」で検索してみてください。

